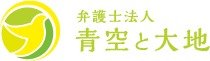こんにちは、弁護士の橋本です。
NHK大河ドラマ「光る君へ」を楽しく観ました。
私は、根気が無くて普段ほとんどドラマを観ることがなく、最後に観たドラマは「半沢直樹」、最後に観た大河ドラマは「龍馬伝」、これだけ熱心に観たのは自分でも驚きです。「光る君へ」は反響が大きく、多くの人がその魅力を様々な角度からコメントしていますので、私が取り立てて語ることはないのですが、少し感想を述べてみたいと思います。
感想その1 現代言葉で語られるので感情移入しやすかった
豪華な衣装の貴族たちが今の人たちと同じような言葉使いで会話していて、そのギャップを楽しみつつ感情移入しやすかったです。
感想その2 配役が素晴らしかった
個性的な俳優さんたちの演技が素晴らしく、どの人物も生き生きと演じられていました。伊周、安倍晴明、清少納言、和泉式部、実資、赤染衛門、隆家といった脇役の人たちの個性、迫真の演技が際立っていました。特に実資を演じた秋山竜次さんが出てくると、毎回、コミカルな演技や表情に笑ってしまい、それでいてドラマが終盤に向かうにつれて重要な役回りを見事に演じていて、共感しながら観ていました。
感想その3 映像が美しかった
平安貴族の衣装や屋敷の映像が華やかで、ドラマ全体を明るく美しいものにしていました。NHKの100カメという番組で、庭を流れる小川に舟を流して歌を詠む場面を詳しく取り上げていましたが、その手の込みように驚きました。
感想その4 多様な要素
物語のメインは紫式部と道長の関係でしょう。恋愛関係と一言では片付けられないものを感じました。恋愛の要素は夫の宣孝、周明、定子、彰子、賢子など色々ありましたが、それだけでなく、道長を中心とした貴族社会の中での権力関係とそれに絡む公任、斉信らとの友情は、純粋なような打算混じりのような微妙な関係で面白く、深さを感じました。権力者道長の親兄弟や妻、息子、娘達、下級貴族であった紫式部の父、弟、娘たちとの家族関係も、我欲や葛藤、対立が入り混じって生き生きと描かれていて、それがいかにも現代的でもありました。
感想その5 人生の学び
主人公紫式部が源氏物語を書き、物語が当時の人たちの人生に深く関わり、1000年後の今も読み継がれています。私は高校の教科書で「夕顔」を読んだのが最初でしたが、1帖では全く理解できませんでした。大人になってから、角川ビギナーズクラシック日本の古典シリーズの「源氏物語」で主要な帖を解説付きで読んで(それだけで全体を語るのもどうかと思いますが)、1000年も前にこれほど大胆な物語が書かれたのかと驚くとともに、時代や環境は違えども、人の営みや思いの本質は変わらないものだと思いました。
最初は母紫式部に反発していた賢子が母と同じく彰子に仕えるようになり、源氏物語を読んで母にその感想を伝える場面がありました。幸せな人は誰もいない、権力者であっても幸せではないといったようなことを述べていました。有名な、「望月の夜」の場面での道長の歌は、権力者の奢りではなく、人生の儚さや無力感を表しているようでした。源氏物語と対比される枕草子は人生の明るい場面のみを描いています。源氏物語は、人生には表も裏もある、陰も陽もある、楽も苦ある、喜びも悲しみもある、ということを伝えながら、それでも人の営みというものを肯定していて、私はそのことが「光る君へ」のテーマだったように、現代を生きる私たちへのメッセージであるように感じました。
ところで、平安貴族をテーマにした大河ドラマは今回が初めてだったそうです。平安貴族というと、権力を独占して贅を尽くし横暴に振る舞った挙げ句、台頭してきた質実剛健な武士に滅ぼされるというイメージが強かったのですが、そのイメージは大きく変わりました。
時代考証を担当した、国際日本文化研究センター教授の倉本一宏先生は、平安時代的なものが日本の基本であると述べておられます。この時代、日本は対外的に攻め入ることはなく、攻められることもほとんどありませんでした。大規模な内戦もなく平和な時代が続きました。平安時代の後に長らく武家政権が続きます。それでは日本は武力が支配する時代が続いたのかといえば、決してそうではなく、支配体制が確立すると平和が訪れ、上級武士は貴族化し下級武士は官僚化したそうです。平和な時代が続くということは、軍事に頼らなくてよくなるので税の徴収が穏やかになり人々の暮らしが豊かになるということです。ドラマの中で道長は常に民の暮らしを考えています。平和というものがいかに人々の暮らしにとって大切なものかということを、この時代に最も理解していたのかもしれません。
倉本先生は、平安時代の後、長く武士の時代が続いたことで平安時代がネガティブに評価されてきた、戦後、マルクス主義的な歴史観が主流となり、歴史の発展段階において武士に乗り越えられた貴族というイメージが定着した、今回の「光る君へ」を通じて平安貴族や平安時代のイメージが変わり、過去を正しく理解し、この国が少しでもよい方向に向かうきっかけになることを期待している旨述べておられますが、その意味はあったように思います。